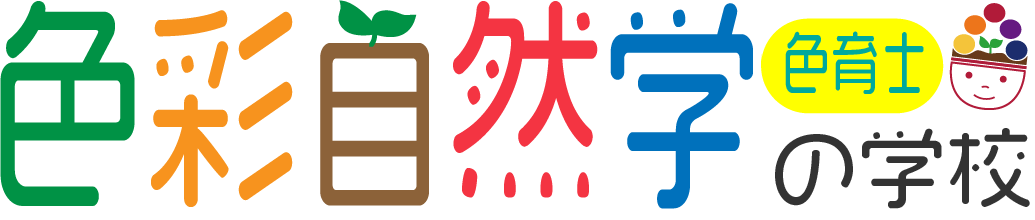色彩自然学について

どんな学びの要素があるんだろう?
〈色彩自然学〉は、ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)[1749-1832]の『色彩論』や『形態学』と、ユング(Carl Gustav Jung)[1875-1961]の提唱する『分析心理学』を礎とし、色の本質的な力を自然ということから探究する学問です。自然の色彩現象から学ぶことのできる色の本質的な力や、人間のうちなる自然としての”心”の深みにある元型像を、自然全体の循環図である『色彩環図』とともに学んでいくことができます。その色がその色であることにまつわる根源的な物語や、無限の生命として巡る自然の物語を探究することは、同時に”自己”を探究することにつながります。どんなに小さな自然も、与えられた場所に根を張って、その生命(自己)を実現しようとしています。自然の1つ1つの生命が、どのように具体的な形態を獲得しながら、1つの存在となっていくかということは、小自然である人間の本質を追いかけたユングや、この世を表現的色彩世界であるとし、自然との関係性において人間をとらえた空海(弘法大師)[774-835]、また他にも生命についてや、人間の集合的物語である神話などを研究した先人たちの知恵にも息づいています。それら生命の表現する色彩の本質的研究を学術領域としています。
色彩自然学ポエム
色彩を万物を生み出す母のような、”自然のことば”として読んでみる
泥の中に咲くハスが、緑色の芽や葉の時をすぎて、大輪の花を咲かせる、
枯れた時には種へとまたこめられて土色になっていく。
地を這う青虫が、その複雑な羽模様で空を飛ぶ蝶々にまでなっていく。
じきにまたほのかに黄色い卵へとこめられていく。
転がり砕ける石ころが、悠久の時を経て、
硬く輝く、ダイアモンドにまでなるという。
その宇宙循環、生命循環、自然の組み上がりの途上に、
「わたし」すらいるのではないだろうか

自然 分身(じねんぶんしん)
「自分自身」とは、誰もが ”自然の分身”ということ
自然の中に私が生かされ、私の中に自然が生きていること
何かを捨てることではなく、何かをもらうことではなく、
すでにあったはずの、かつてあったはずのものを再発見すること
その気づきを、色という自然のコトバは、いつなんどきももたらしてくれる。
自然とともに、人が生きていくための太古から紡がれてきた大切な知恵として
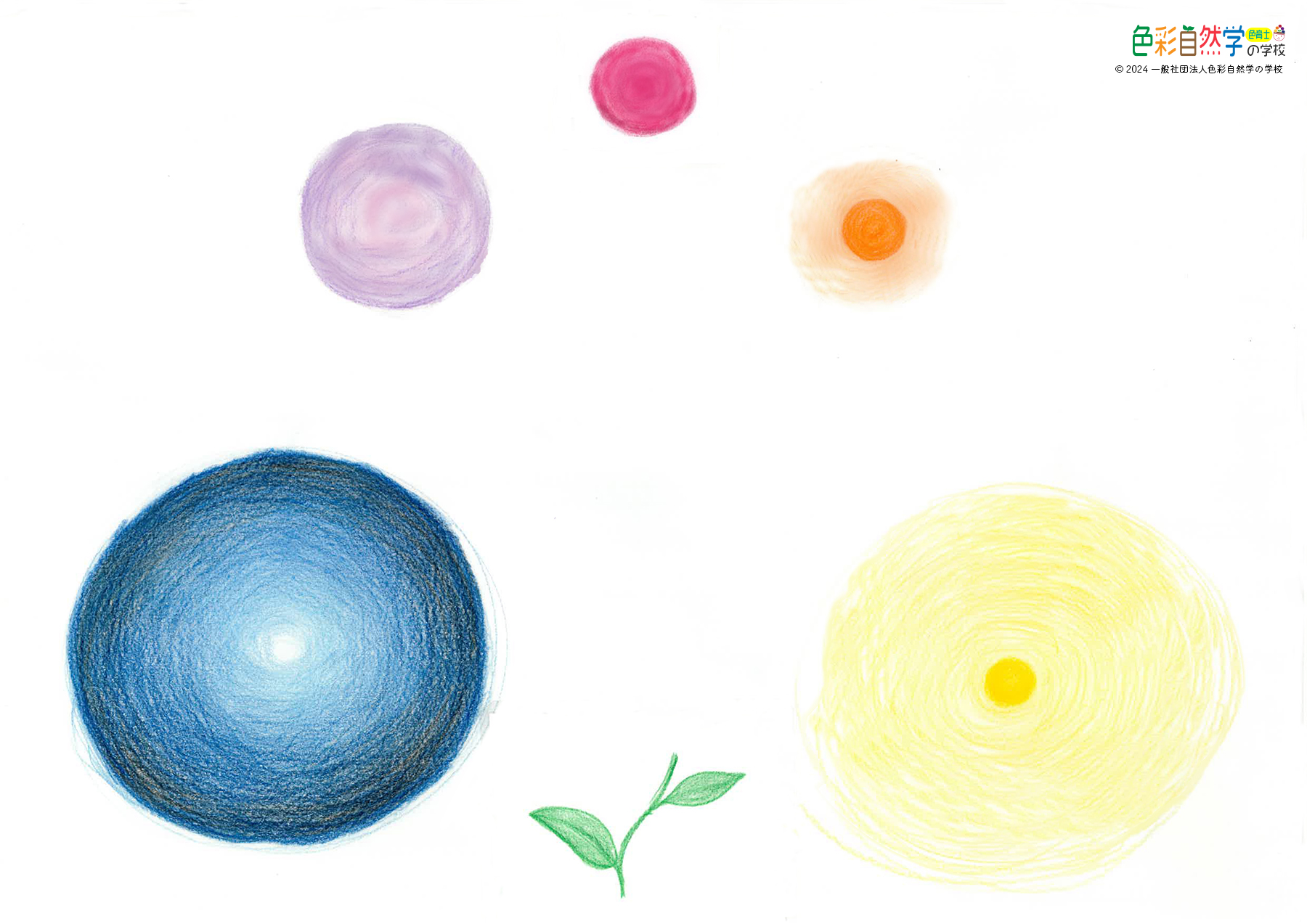
まだ新しい学び?色彩自然学
〈色彩自然学〉ということを始めるにいたるまで、社会人になった私(代表 髙橋)は、15年あまり、日本色彩心理学研究所で〈色彩心理学〉の分野を研究、実践していました。色彩を用いた表現創作活動によって、健康な人から不登校の子どもたち、精神疾患のある人たちまで、それぞれに心の中にあるものを映し出し、その表現が、少なからず彼らの心的現実を揺らしたり動かしたりして、その人らしさに接近することに役立っていたことを確信しました。そういった探求の中で、ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)[1749-1832]の『色彩論』や『形態学』に出会い、次第に色と心という範疇だけでなく、植物や動物や鉱物と色との関係、ひいては色と自然、色と生命とのつながりに興味が拡大してゆきました。自然のあらゆる生命たちを突き動かしている、原理的で根源的な力を、色という言葉から学ぶことができる〈色彩自然学〉の新たな展開を、大学の先生の助言をいただきながらはじめたのが2020年です。
どうしてエキスがゲーテなのか
世界の色研究の潮流を辿ってみます。
紀元前4世紀頃には、古代ギリシャで人類最初の「色彩論」がアリストテレスによって著され、自然の光と密接に関わった色彩世界観が語られました。
また、18世紀にはニュートンによる『光学』が著され、光を分解し、色光ということを考えることになり、我々は色のしくみを知ることになりました。
このニュートンの貢献により、私たちは生活に色彩を取り入れ、楽しむことができるようになりました。
この頃から、近代科学は急速に発展してゆき、ニュートンは色彩を合成可能で定量化できる物だと、科学の研究対象としました。
ニュートンと同時期に、ゲーテによる『光学論考』が著されました。
”色彩は、光と闇との相互作用によって生まれる”という色彩の本質が示されました。彼は続けて『形態学』や『色彩論』を著し、人間を含む”自然”というもののもつ創造力について、また、自然のもつデモーニッシュで圧倒的な力と人間との関係性について伝え、自然は究め難いものであるし、生命としての自然を定量化はできない、と主張しました。「光は、精神と同様、分解などできるものではない」という主張をもって、ゲーテは、色彩を含めてすべての自然が科学至上主義の中でコントロールできるものと掌握されることの警鐘として、自然を分解し、人間の都合だけで利用しようとする立場のニュートン光学を批判しました。

色彩を研究することには、ニュートンとゲーテという、この2人の功績が、現代に根強く息づいているのだと思います。
色彩を分解可能な色光とし、プリズム実験により色を物質的なものとして研究することで、近代科学の発展に大きく貢献したニュートン。
そして、色彩を光と闇との相互作用とし、あくまで自然への畏敬のもとで、自然を分断することなく、観照することから生命の公式を見出し、生きた自然の研究に貢献したゲーテ。
「色彩」を研究するには、この二人の素晴らしいポルタージュがあります。
〈色彩自然学〉は、ゲーテの方法論に基軸を置いている学です。
色彩がかたる”自然”というものの持つ力やふるまい、在り方や創造性を、人間の内にも発見し、自己を拡充深化させていく学問です。なぜなら私たち自身が自然の一部であるならば、この学びの中でこそ、学んでいる人間を調和した自然の全体性(自己そのもの)へと、一歩ずつ近づけてゆくことが同時にできるのではないかと思うからです。自然とともに歩む個人を、”色”という視座から、息づかせていくことができます。
近代科学の発展によって代償となったものが”魂の豊かさ”であるならば、ゲーテ的な自然観によるものの見方や考え方、自然とともに歩くことや、自然への畏敬の念を、私たちひとりひとりが取り戻す必要があると私たちは考えています。