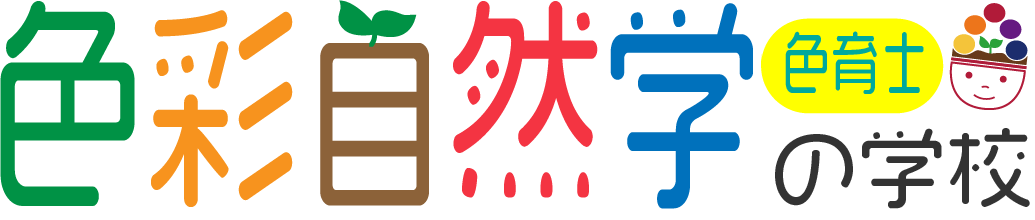自然農(無肥料無農薬栽培の研究)3年目。
私はなにを自然農と言っていいのかわからないため、”野良農”と呼んでいる。
少しずつ、腐植に還っていく有機物たちと共に
作物が育つようになってきた。


はじめてニラの種とりができた。種ってきれいな黒色、黒光をしているなと思う。
来年にまたつなごうと思う。

小松菜の成長が溢れだした。味もとても濃ゆくて美味しい。
やっぱり土が本来的に元気で菌類や微生物がたくさんいる環境にあると、作物たちは味が濃ゆくて美味しい。その場で齧って食べれる。鉄分もたっぷりある味がする。

びっくりしたもう1つが人参。
見た目はよくないけれど、甘くて濃くて驚いた。次は、人参と対話して少し大きくは育ってほしいと思う。

植物たちが土に還っていくのはやっぱり闇側のエネルギーにのっかることだろうから、月が満ち欠けすることときっと同じで、根気強く「待ち望む」という方法がそばにいる人間としても必要になると、私は考え始めている。
少なくとも、死と再生のような変容が土の中で行われていくのだから。
それは時間と大きな転換が起こるだけの条件がそろわないといけない。
つまるところ、今強く思っていることは、「待つ」ことが野良仕事の1つでもあるということだ。
人間が土や作物に働きかけて、対策を講じているばかりではなく、自然が何をやろうとしているのか、その声を聴く心の構えのようなものが必要なのだと感じている。虫がいっぱいたかって白菜が齧られてしまうと、おろおろと狼狽えてじたばたしてしまう。でも、じっとそれを見守ってみることも実際に大切なことだった。

実際に私の白菜はどれだけ齧られたか知れないけれど、今、安定しはじめた。やはり暦通りに苗を植えることよりも、気候の不規則な動きと呼応して、自分の肌で感じて適期を見出して植えていくことが問われている気がした。
生態系や循環の力を尊重した暮らしがしたい。それは色彩自然学を研究してきて、色は循環の言葉だと知ったから。それを暮らしに、と実践したくてチャレンジしているものの、道のりは甘いものではない。なにせ実際の生活がある。生活は現代のやり方にのっからざるを得ないところもある。
うまくいかないことや、行き詰まることもあって、一度全部の手をとめて、海を眺めに行ってみたりもした。
そこで目にする海が、往来する波音を繰り返していて。その音に身を任せて過ごしていると、
行ったり来たりしているのは表面のことで、その海底では揺るぎない潮流があることがわかるような気になった。やっぱり私はやめることはできない、この道を。たとえ報われずとも、たとえ何の役に立たずとも、信じたことを形に残していく。

畑でであった、僕よりも20や30や歳上の先輩たちが、少しずつ僕ががやろうとしているどうしようも面倒くさいことを、理解できなくてもそっとしていくれているのがわかる。
いろいろ差し入れをくれたり声をかけてくれる。ありがとうございます。
教えている学生たちともいつか一緒に何かをやれたらいいなと思う。
こうゆうこと言葉にすると最近涙が出てくる。年とったな。
学生たちと描いた月の絵を最後に、この投稿を終わろうと思う。