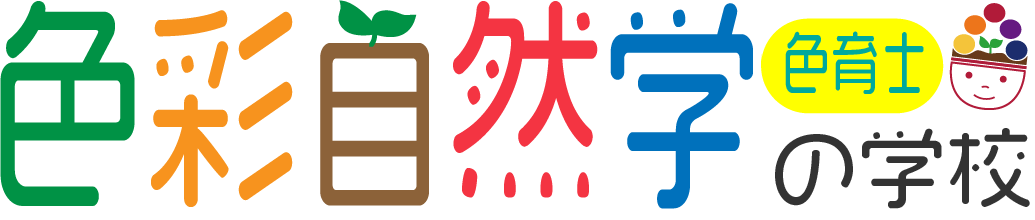自然循環のなかに生きる
無農薬、無肥料、土の力を取り戻す農のあり方へ
2022年の暮れより、色彩自然学の学校は、自然栽培の畑を始めました。また2024年より土(つち)本来の力を尊重した農「野良農」と称して、実践をはじめました。今、地球上の肥沃な土が減ってきていると、日本の土壌学者の藤井一至さんがおっしゃっていました。これから先の地球は、美味しい野菜や果物が今までのように手に入る地球ではなくなってしまいそうです。それを受けて自分たちができることは、土の腐植を増やして資源循環を促進することです。私はこの「土の腐植を増やす」ということを、足元からできる限り実践できるようトライしています。具体的な目的は、土の腐植を増やし、肥沃な土を取り戻すことです。人間が自然とともにある暮らしを立てるために、資源循環ということを基軸に持つ必要があると思っています。
20年にわたり色彩の声を聞くことで、自然の諸力についての関わりを深めてまいりました。色彩は環のように始点と終点が重なりますが、それが自然界の運びをも表していて、作物が花を咲かせ、枯れて落とした最後に種子が作られ、その作物としての終焉がまた、次の生命の始まりにつながる、終わりと始まりの結びつき〈環〉が巡ることと同質の学びがあります。
畑は、色彩の両親でもある光と闇のエネルギーが生き生きとその役割を見せて、緑の若芽が結実した赤い実をならしてバトンをつないでいく生きた色彩の学びでもあります。
どの色にも自然の役割があるように、畑においても起こることで必要のない現象はひとつもないことを思います。すべてが、その畑が豊かになるために起こってゆきます。大切なことは、畑が調和と全体性を営めるように、自然の運びを人が知って、それをそっと助けることだと思いました。
本校の目的は、人類の喫緊の課題とも言える「自然とともに生きる」ことに、色彩自然学から取り組むことです。色から学ぶことや、野良農から学ぶことは密接につながっているので、自然破壊について自分ごととして捉える心も、自然とともに生きていく心の構えも、自ずと育まれる気がしています。
このような精神で、色の研究や教育の傍ら、腐植を増やす野良農実践をおこない、その総合で、人間が自然とともに生きられることを回復していけるよう、牛歩のごとく取り組んでまいりますので、できれば末長い応援とご助力をいただけますよう、お願いいたします。