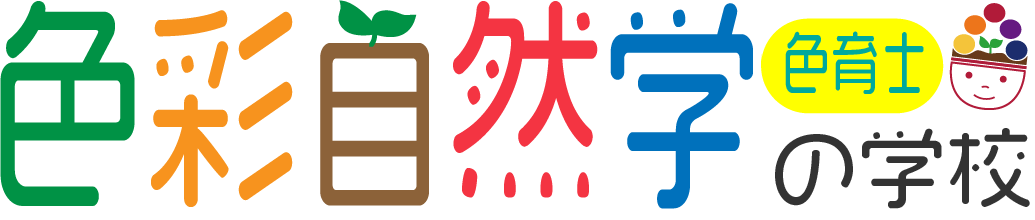やっと梅雨がやってきた。梅雨を迎えると、畑のきゅうりが喜んでいるのか、驚くほど彼らは太る。
梅雨が心身にもたらすもの
ここ数日でも、いろんなことがあった。でもあまり考えることはぱっとしない。
梅雨は体や心に、湿気を帯びた重たさを運んでくる。しとしとと降る雨や曇天は、内界における水分変化と切って切れない。そういえば、私は最近、はと麦茶を無性に飲みたがる。はと麦茶は水を外に出してくれるらしい。
この時期は、これからやってくるだろう”かんかん照りの毎日”を前に、いろんなことをひとまず曇らせ、水にくぐらせて、濡らすだけ濡らしていくように思う。濡れると、いろんなものとの結びつきが色濃くなっていく。顔をのぞかせるネガティブな自分も、自分をつくるための構成要素。地下室にこもったあの願いをかなえる魔人も、行き場をなくしたとニュースが叫ぶ野生動物も、自分の中の一部のことなのだろう。


「当事者になれ」と叫ぶ声が、年齢を重ねるとともに自分のなかに響くようになった。
世界で起こるニュースも、家族で起こる出来事も、自分の小宇宙の出来事として、響き合わせて捉えていく。でも、それが全てになってもそれはそれできっと良くない。自分とニュースや出来事を切り離してやっていく視野も、雑事をこえて生きぬいていくには必要なんだと思う。
ただ、私たちはずいぶんと当事者になる知恵を、失ってきたのではないだろうか。面倒なことから自分たちを切り離し、効率や利便性に偏ってきた代償は、きっと現代人の精神にまで及んで、今の自然と乖離しがちな世界を作ってきたんだろうと思う。
よもぎの葉で止血
最近、私のいろいろあった出来事の1つとして、「鎌で指を切った」ことがある。それは血に塗れた痛い経験なのだけれど、同時に、「よもぎ」との忘れがたい出会いがあった。

草刈り中に鎌をふりまわし、人差し指の第一関節から第二関節あたりをグサっと切ってしまった。手袋を突き破って、傷口は深く、なかなか血が止まらなかった。血溜まりができていく。どうしたものか、と、ティッシュで傷口を圧迫していると、畑で知り合った方が「あらー、大丈夫かいな、よもぎ!」とよもぎを探し出し、両手でそれを絞り始めた。
「よもぎで血止まりますよ。」
と。その方は、小さい時に擦り傷や切り傷で血が出たときによくやったらしい。
私は受け取ったよもぎを、まだ止まらない傷口におしあてて、半信半疑で、藁をもすがる思いの中、圧迫して数分、
あれだけ止まらなかった血が、止まった…..
嘘みたいにぴたーっと止まっている傷口に、ただただ感心しました。
やっぱり、こうやって体で知れるとほんとうに深くで知れるなと思う。もう疑う余地がないし、よもぎへの関心が高まっている。
私は今も治っていない傷が痛いのだけれど、それと同じだけの感動が、心の中でないまぜになっている。こうやって1つ1つ自然との関係性を修復していく道があるのだなと思う。
よもぎの何が血をとめたのか?
古くから、
- ヨモギ
- どくだみ
- イタドリ
などの代表的な3つの野草は、民間薬として、擦り傷や切り傷などの止血に使われてきたそうだ。
私はこういうことをやっているけれど理系出身で、やっぱり調べてしまうのだけど、今回私が止血で経験したのは、ヨモギに含まれるタンニンのおかげがあったそうだ。
タンニンには収斂作用があるため、血管や組織の収縮を促す
”収斂”(しゅうれん)というのは、まさしく色彩自然学で自然の本質的な力を学ぶ際にも出てくる、自然の”つぼむ”働きのことだ。反対の働きには、「花」でいうところの”開花”があると考えていい。”収斂”というのは、花が開く前に蕾がつぼむときの、その”つぼむ”働きのことだ(正確には、花は開いたあと、種をこめるときにも”収斂”する)。「虫」でいえば、”蛹”になるときの働きでもある。
”収斂”とは、色彩自然学なりに言えば、同時的にも経時的にも、開いた変化が起きる前提の収縮作用のことだろう。
実際に私は、こういった怪我をしたとき、血が止まらないということがどれだけ恐怖かを味わった。
ぼたぼたと落ちる赤い血は、本来出てはいけないものが流れ出ている感覚がおこる。
これを止めなければ、次の行動にスイッチが入らない気がする。
実際に、血が止まらないうちに傷口を流水で洗うことに、気が進まなかった。
特に今回は、緑の畑が広がる場所で、赤い血がほんとうによく目立ってしまって、これも補色の作用だからこそあまりに生き生きと見えるのだけれど、動揺している自分もいたと思う。
こういう時は、まず血が少しでも止まることが大事なプロセスだったと思い返すと、よもぎの有り難さが身に染みた。
そこでよもぎという止血ヒーローに出会ったことで知ったことを、備忘録したいと思う。
〈備忘録〉よもぎで止血の手順3つ!
① よもぎを見つけよう!
よもぎ、みなさんは見つけられますか??よもぎにはどんな特徴があるのでしょうか。

- 裏面は繊毛が密集しているため白っぽい色(白い産毛)
- 葉っぱ互い違いに生えている(互生)
- 葉っぱは深く切れ込みがあり、一枚一枚が羽のように見える
- 表面は鮮やかな緑色

最大の特徴は裏面の白い産毛です。
② 手でよくすりつぶし、液をだす
手の平や指を使って、よもぎから汁がにじみ出てくるように、揉み込んだりすりつぶしたり、雑巾しぼりのようにしぼってみるのもよかったです。よもぎのエキスがでてくるように、もみましょう。
③ 患部に、よもぎごとあてよう
血が出ている傷口や患部に、すりつぶしたよもぎをあてて、血が止まるまでしばらく指圧。
圧迫のポイントは、傷口や患部を点でとらえて、その患部の点をよもぎごと、ぎゅーっと指圧するのがポイントだそうです。例えば指先を切ったとして、指の根本をひもでしばる、などはあまり良くないそうです
血がとまるまでおさえ、血が止まったら患部をよく流水で流して、ガーゼや絆創膏などで傷口が乾燥したり菌に感染したりしないよう、保護するとよいそうです。消毒することよりも、流水でしっかり汚れや土など付着物を流し落とすことが先決だそうです。傷口が開いている場合は、菌がそこから入りやすくなるため、ガーゼや絆創膏などで乾燥しないように保護するようにするといいそうです。
あとがき
よもぎは、その繁殖力や生命力の強さから、この世に最初に生えた草とも言われた歴史があるそうだ。
また、”よもぎもち”などで知られるように、各地で食すほか、芳香からも霊力の強い草としても知られ、魔除けや邪気払いにも利用されてきたそうだ。
今回はそんなよもぎのもつ力と怪我をとおして出会え、痛い思いはしたけれど、自然とともに生きるということは、共生だけでなく、共苦ということもあってこそだと感じています。
自然とともに生きるというのは、きっときれいごとだけではないですね。少し不便であったり、面倒であることの中に、自然と共に生きる知恵や私たちの本当の意味での”健全さ”のようなものが見つかるのだと思います。
すぐに薬があって、絆創膏があって、便利な現代に住んでいるけれど、本来は薬も、土や自然から抽出したものであることを心に刻んでいたいなと思います。抗がん剤ですら、きのこたちの成分なのだと、父の闘病のときにはじめて知りました。
長い文を、読んでくださりありがとうございました。