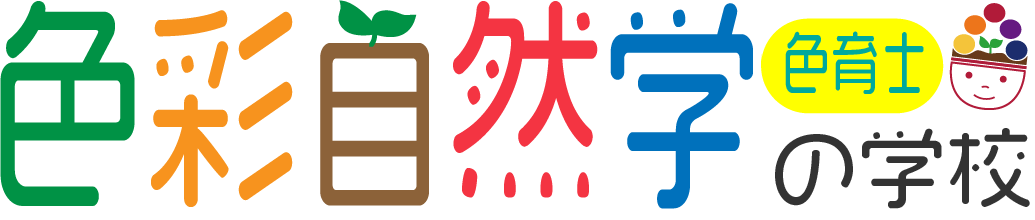”皆既月食”。”既”という文字には”〜し尽くす”という意味があるそうだ。”皆”は”すべて”。
月全体が、太陽の影に覆い尽くされる、”皆既月食”を撮影した。写真とともにコラムします。
日食と月食があるけれど、
”日食”は、太陽と地球の間に月があった。
地球からみて、月と太陽の距離も軌道も違うのに、日食の瞬間にはみかけの大きさが同じになることが不思議すぎて私は口が開きっぱなしだったのを覚えている。さらに、日食の瞬間、あたり周辺が静寂に包まれたという報道があったことも、印象に残っている。
さて、今回の”月食”はどうだったかというと、”色”に魅せられた。
前日9月7日の9時頃の月。
ここ神戸の空では雲が多く、雲間から月を見るといった具合だったが、11時頃になると雲も少なくなり、まんまるとした月が顔をだした。

月は”テイア”という惑星が地球にぶつかることから誕生したとされているが、
月面のボコボコとしたクレーターも、約10億年前まで月の表側(地球を向いている側)が活火山で覆われていたことの証だそうだ。宇宙はしっかりぶつかり合うことで、何かを生み出してきた。私はすぐに、自分はどうだろうと考え込んでしまう癖がある。自分も何かとぶつかりあえれば、何かを生み出せているのだろうかと。自分も惑星気分なのだ。
ちなみに9月7日の月も、月面を見たいがために撮影してみた(次の写真)。

火山の跡のようなものがみてとれる。地球の周りを回りながら、火山が噴火していたことを想像してみる。今の月は、十分に冷えたらしい。
そして、9月8日(今日)、皆既月食の月は、午前3時〜3時半の間に撮影した。
赤銅色と言われているが、そのとおり、赤色なのだけれど、重たさや深さを感じる赤色だった。

まるでイラストのようだが、実際に撮った月の写真。
これを見られるということは、今、私のたつ地球の正反対に太陽があって、太陽ー地球ー月と、一直線に並んでいるということか。ふと後ろを振りかえってみるが、そこにはベランダの扉がある。でも、そのずっとずっとはるか向こう、裏側に太陽がある。その向こう側の太陽の輝きを受けて、地球をとおして、月が赤く染まる。
なぜ、赤く染まるのか。それを科学的に知ることはネット検索すれば誰もが可能だろう。波長の話が出てくる。でも、それで納得する好奇心以前の、古くどうしようもない好奇心を私は持ってしまっている。
たとえばかつて活火山を持っていた10億年前の月は、こんなふうに赤らんでいたのだろうか。だとしたらかつての姿をほんのひととき、月が取り戻しているようで、大切にしたいシーンにもなってくる。
たとえば月が引力をもって地球の周りをまわっていて、その引力で海面が引き上がるため、潮の満ち引きが起こっている。そしてそれが我々の血潮の流れや、母胎、肉体にも、ふかく関わっていること。宇宙と呼応して生命があることへの畏敬の念。こういったことは、理屈とか原因結果というものさしだけではないところのものなので、自分が感じる心を開き、類型をたどること、誰かの言葉を聞いたり、観察し尽くしたりすることが、ほとんど私の仕事の中身になる。
目の前で月が赤くなっていることに、阪神淡路大震災の前の日の夜の月を思い出した。あの前日の晩に、赤い月を見たと言った人は、私のまわりでも少なくなかった。
そして、自然界の動植物たちが、少しずつ赤色(褐色)を帯びながら絶頂へと向かっていく様子を観察し続けてきた私にとっては、行き着く赤が”終焉”でもあることを感じざるを得なかった。
ことが終わるということは、またそこに新しく始まることも相まって起こる。
歴史的にも個人的にも、長く手にしてきた何かが手放されるとき、変化する兆しがあるのではないか。
そうして私は、つい最近、5年ほどあたため続けてきた1つの取り組みを、終えることを決めた。
生きるということは生かされるということでもある。
運ばれてくるものに呼応することは本望だ。変化することが、そのまま生命の取り組みでもある。
自然とともに生きることにできる限り生命を使いたい私は、これから赤い月と出会うとき、どんなことになっているだろうか。そしてこの地球は、どんな時を迎えているだろうか。