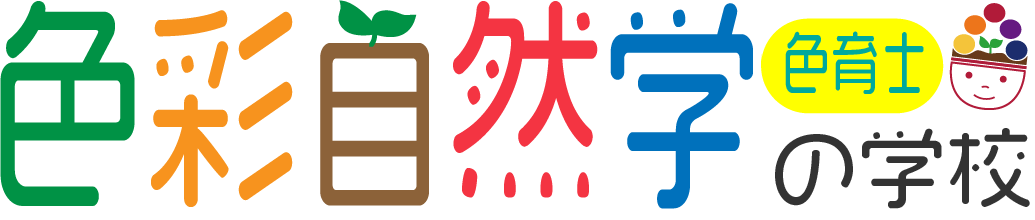家のレモンの木にやってくるようになって、3年目の黒アゲハやナミアゲハ。
今年は、猛暑のなか、無事に4匹が羽化して飛んでいった。
一度ここから旅立った経験のあるものは、どこへ行ったとしてもまた、育った原点へ戻ってきて卵を産みつけると言われている。
今年も、なかなかの数の黒アゲハやナミアゲハが、レモンの木に卵をうみにやってきていた。それは3年前、「メタモルフォーゼの観察がしたい」という私のエゴで、レモンの木に偶然やってきたナミアゲハの卵を1つのこらず(20匹近くを)自宅で羽化させたのが原因だ。20匹の羽化までの世話は、ほんとうに大変だった。なかでもプラケースの中の糞の掃除が忙しくて、青虫の食欲がすごくて、途中から私は日々何をしているのか、わからなくなったこともあった。
今年もうちの猫は、窓越しに「ケッケケケケ」とクラック音のようなものを鳴らして、アゲハの到来を知らせ、興奮している。あの3年前に一度、家の中で知らない間に羽化してしまったナミアゲハを、彼がジャンプ一撃で叩き落とすという惨劇があって、私は茫然自失で涙したこともあった。悲しいやら腹立たしいやら、でも、猫さまの本能を責めるわけにはいかない。怒ったけど。そのときは手を合わせて合掌して、なんとかことを過ごした。それ以降、彼は窓越しにいて、アゲハの到来にいちいち興奮している。
今年は様子をみながら4匹だけ羽化を見届けた。アゲハたちのたまごを産み落とすことを回避するために、ニームオイルなるものをふりかけて、レモンの木が幼虫たちに食い潰されないようにしている。もし、産みつけにきた卵の数だけ羽化を手伝ったとしたら、私の家はまた”アゲハの里”だ。



今回は、クロアゲハが3匹、ナミアゲハが1匹だ。最初は鳥の糞のように擬態して(写真1:クロアゲハの幼虫)、何度か脱皮をして、青虫になった途端から、食事の量がとてつもなく多くなる(写真2:食欲旺盛なクロアゲハの幼虫)。一生懸命に葉を食んで、糞をすることをひたすらに繰り返していくと、体色の緑がどんどん濃くなっていく。そして、いざ蛹化へ向かう。
合図は、体内の水を全部だすこと。そうすると、蛹化に適した場所を探すために、ケースの中をひたすらに歩き回ることがはじまる。その歩き回る隙をみて、糞や葉っぱをすべて取り除き、蛹化に必要な支柱となる割り箸や木の棒を用意してあげるといいことが三年目にしてわかった。
蛹化の場所を探して歩き回っている間、青虫の体色が、濃い緑から、光るような黄緑に変化する。メタモルフォーゼが近い合図だけれど、私はこのときにいつも不思議な感覚を覚える。手を合わせてしまう。このことがうまくいくように願いながら、次にどんな風にことが運ばれていくのか、それを見せてもらえる喜びが静かに湧き上がってくる。自然が秘密の何かを開示してくれているような喜びと感謝がある。
私が思うに、自然は機械で再現できるようなものではない。コントロールできるものでもきっとない。神の息吹のような、人間の意識では及ばないような不思議があって、触れることや知ることがどこか恐れ多いような何かが、そこにはある気がする。これを霊性とか、ヌミノースとか、畏敬の念とか、先人たちは言ったのではなかったか。
私たち人間は、知りたい欲がとても強い。でも、すべて知れることがいいことでは決してないんだと思う。手を合わせてそっと祈ろう。そんな感覚を澄ませて、「ここまでだ」と感じられることも、生きていく上では大切なんじゃないだろうか。
ようやくアゲハたちは、蛹という長い期間を過ごす場所を選んだら、腰をおちつけて羽化という大仕事にむかっていく。紐を口から出して支柱にかけて体を固定する。(写真3:クロアゲハの蛹化)その体を振りながら糸をかけていく様子は、本当に神秘的だ。

無事に蛹化を果たしたときの彼らの写真が上の写真だが、下に落ちている殻は、蛹化した際の脱皮の抜け殻だ。緑の蛹と、茶褐色の蛹とがあるが、置かれた環境によって蛹の色に違いがあるらしく、それも面白い。バッタにも緑のバッタと茶色のバッタがいるけれど、それも同じ理由だった。


写真5と6は、羽化が近づいて、蛹の色がだんだんとアゲハ蝶の羽の色に透けてきているところ。ここまでくると、中にいるアゲハの息遣いが目に見えるようになってくる。
よく「蛹の時期には動かないのか?」と質問されることがあるけれど、蛹の時期には全く動かないわけではない。時々、ピクッと動いたり、体を左右にふったりすることがある。でも、その場からは何があっても動かないし、体を支える紐も、とても丈夫につながれている。
羽化の合図は、蛹の色が透けてくること。中のアゲハが透けて見えてきて、頭部に目のようなものが認められ、”蛹の殻”と”蝶々の体”との間に隙間が生まれ始めたら、羽化間近だ。
羽化のとき、彼らは殻を一気に脱ぐ。今まではなかった長い足で支柱につかまり、まだ濡れている羽を乾かすためにだらーっと羽根をたらす。下の写真は、羽を乾かしているところ。



同じクロアゲハでも、やっぱり羽の色や模様の出方が個体によって違う。
最初は地を這い、のそのそと動いていた青虫が、まさかの空を飛ぶまで飛躍した生き物へと成長を遂げる。それは、天と地ほどに違う世界をつなぐことのできる物語ではないだろうか。蛹化から羽化の神秘は、何度見せてもらっても感動する。
わたしたち一人一人も、同じ生命をもっている。生命という点では、わたしたち誰もが、彼らと似た物語を生きているのではないだろうか。どこかで蛹化のようなことをして、まるで周りから見ればサボっていたり怠けていたり、なんらなんの動きも感じられないような閉じこもった時期を過ごしたりして、それが何の意味も成さないなんてことは、ないのではないだろうか。それはすべて、自分自身になるためのメタモルフォーゼの準備なのではないだろうか。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
アゲハの蛹化や羽化を自宅で体験したい方は、私のやり方でよければいつでも教えるので、気軽に聞いてください。お子さんだけでなく、大人も。