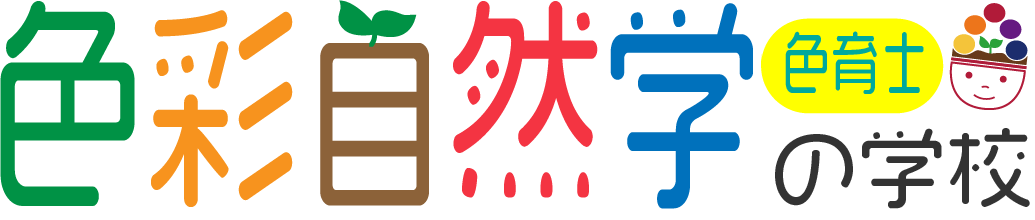この秋から、色育士へチャレンジしてくれる方が2人いる。その報告と、応援のために投稿させてもらいます。小さな学校なのに、学びを続け、チャレンジしてくださりありがとう。
心の柔軟
私は最近、”股関節の柔らかさ”が大切なのではないか?と遅ればせながら柔軟をはじめた。
ふと、体だけではなく、きっと、心の柔軟運動も大事だよなと思ったが、私たちはなかなかそれをどうやっていいのかわからないところがあるのではないだろうか。
日本人は、セラピーやカウンセリングを受けることに恥じらいがあったり、どこかレッテルをはられてしまうような感覚が強いようだが、私は正直、「そんなこと言ってられんやん」と思っている。
自分の心のバランスや柔軟性は、自分でなにかしらを取り入れて、なんとか世話していくしかないのではないか。自殺率の年齢別の推移を眺めながら、それが喫緊の課題であることを感じている。
この近代科学の発展により犠牲になってきたもの、切り捨てられてきたものは大きい。それが個人の中にも澱のように積もっているのではないかと思う。私たちは知らない間に傷ついているのではないだろうか。知らない間に拒絶されて、知らない間に搾取されている。それは阪神淡路大震災で被災したときにも思ったこことがあって、その傷がまだ疼いているように思う。
色育士の仕事と背景
勝手な前置きで失礼したけれど、そんな世の中の心理支援にとりくむ「色育士」に、今回2人の方がチャレンジしてくれることになった。色育士は、色をつかって、色塗りをした簡単な絵を描いたり、イメージを外在化していくことで、心の中のことを整理したり、おさまりきらなかったものを、無理のないように心におさめなおしていく、おさめられるような形にまで対話していく、その作業を手伝う専門家だ。
彼らはそんな専門家でいるためには、自分自身が”心”にいろいろあることを知識としても、経験としても少なからず知っていなければならないし、自分で色をとおして心が揺れる生活を心がけていなければならない。そしておそらく、彼らは誰よりも、病気まではいかずとも”心が病む”ということ、心の未病という状態について、身近に感じたり、身につまされることがあったのだろうと思っている。
チャレンジをありがとう
うち(本校)は小さな学び舎なので、1人でも2人でも色育士になりたい、チャレンジしたい方がいるなら、できるだけその時期にチャレンジできる門戸を開いておきたいと望んでいる。でも今回、2人いてくれてよかった。色育士になるために、3ヶ月程度の短い研修を組んでいるが、その期間中に同期の仲間がいることは、きっと互いに励まし合ったりもできて、悪くないことではないかと思う。
9月の後半あたりから彼らの研修がはじまる。今回のように若い方々が、色育士ということに携わって、自分たちの技としてそれを切磋琢磨したり、発展させていってくれれば嬉しいなと思っている。
互いの軌跡に敬意をはらいあい、自己実現を支援できるような関係性を結んでいきたいといつも願っている。なかなかそれがうまくできずに、悩むときも多いですが…
読んでいただきありがとうございました。
ぜひ、色育士にチャレンジしている方々、また現在、色育士や公認色育士として、頑張っている方々を、今後とも見守り応援してやってください。
よろしくお願いいたします。