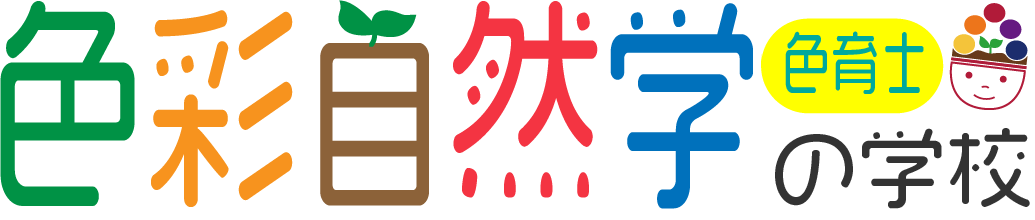こんにちは、これを書いている今はもう17時過ぎだから、「こんばんは」ですが、みなさんは今晩の晩御飯は何にしますか。我が家は焼売の予定☺️です。
シューマイには、チーズをあわせて食べると本当に美味しい。晩御飯が楽しみだなんて、戦時中や戦後のことを知れば知るほど、幸せなことだと思います。
このホームページのことですが、トップページを少しリニューアルしました✏️
これを読んでくださっている方も、そして初めての方も、
少しでも見やすく、わかりよく、たどりやすくなっているといいなといつも思います。
動物園や植物園のような生きた仕掛けを、できることなら作ってみたいけれど、私の技術では当然できません。
生き、生かされて
今回ホームページ作業をしながら思ったのですが、私は前身の日本色彩心理学研究所の頃のものも含んで、何千回とホームページをリニューアルしたり触ったりしてきたんだろうと思います。
ホームページを作る側も人間だから、いつも整理整頓に向いているわけではありません。
だからこの道のプロの人たちは、入念に計画を立ててHP作成にとりかかるわけでしょうが、私はそれができません。年をとるほどに諦めることも肝心です。時には少し頭が明るくて、整理できそうな時もあるんですが、たいていの私は”曇り”で翳っているのが通常運転。だから、鮮やかなものはより鮮やかに感じられるという点もあり、写真を撮ったりすることは息をするようにできるようです。
そういうような不完全な生き物として、私はこの学校のホームページを作り続けさせてもらっていると、いつも自分自身の変化や、関わってくださる皆さんの変化、時代の変化にも応じたくなってしまって、小さなリニューアルを続けています。
今も黄色のアンダーラインを施しているその右手が、一体何を基準にそのアンダーライン箇所を決めているのか、自分でうまく説明できません。私の何かがそれを大切だとアンダーラインしているのだと思います。こういう仕事を本業としていると、ほんとうに世の中に起こること、自分に起こることについて、説明できないことの方が多いです。生きているだけでなくて、生かされていることを、感じ入ります。自分の意思でこうしよう!ああしよう!と目的志向で進むも「私」、偶然のできごとに巻き込まれながら、周りからの要請で思っていたようなことにはならなかったも「私」、その総合で、「私」ができあがっていくと思い当たります。それは「私」だけでなく、自然の生命たちはみんなそうなのだろうな、と思います。
ヒメコンドルに会う


最寄駅近くの大きな公園に、触れ合い動物園のようなものがやってきました。おかげで、「ヒメコンドル」に会うことができました。彼が後ろ向きでいたところを、背中をじーっと見つめていたら、こっちを向いて、羽を広げてくれた。相当に飼育されて手なづけられているのか、と少し残念な気持ちで足元を見ると、鎖でガチガチに繋がれていました。きっとどれだけ手なづけられていたとしても、ふとしたときに沸き起こるような、野生はまだまだ残っているのでしょうね。排除しようとしても、そんなことができるもんじゃないことを、私たちは忘れてはいけませんね。
ヒメコンドルは、鼻に穴が空いていて、見た目にも頭部のみ禿げて、肉色のような肌の赤が露出している。羽は大きく黒くて、お世辞にも可愛いとは言えない、恐ろしい容姿でした。夜に暗がりで道で会ってしまうと、きっと叫ぶでしょうね。視線を合わせ見ることも、明るい時間でも怖かったです。目が黒かった。
ハリーポッターが好きな人はわかると思うのですが、「あの人」(ボル○モート、大きな声でその名を呼んではいけませんよ)を彷彿とします。もしかして彼のモデルはこの鳥だったのではないかと、ふと思ったほどです。「ヒメコンドル」は腐ったものを主食とする鳥だそうで、それを知らなくても、その姿形や動き方で、闇のエネルギーを持っていることはわかりました。
動物にも光のエネルギーを強く感じるものがいるように、闇のエネルギーを強く感じるものがいますね。
それにしてもこの触れ合い動物園には、蛇やヒメコンドルまで野外でゆるく触れ合える中で、小動物もそこそこいて、なかなかたくましく、混沌とした、不思議な移動動物園だなと思いながら帰ってきました。
生まれたての緑


自然栽培、自然農に挑戦している当校ですが、畑は端境期を越え、ようやくにぎやかになってきました。進捗は別の投稿でさまざまな写真とともにお伝えします。
先の写真は、畑に定植したパクチーが冬超えをして花を咲かせてくれました。うっすらとあからんだ淡い紫色の花弁で、その1つ1つの花の形がまた印象的でした。葉っぱはしっかりパクチーの香りがしますが、花はあまり香りません。
次の写真は、畑のいたるところで点々と赤紫蘇が芽吹いています。紫蘇はつないでいく力が強いなと思います。その赤紫蘇の葉の上に、生まれたてだろうバッタが乗っていました。

体表の水分が行き渡っていないのか、しわや撓みをその肌に感じるように思います。生まれたての人間の赤ん坊そうなのでしょうか、しわしわに見える。ほんとうに小さくて、柔らかい緑色をしていました。そっと顕微鏡カメラで撮らせてもらいながら、これからきっと、緑も濃くなって体付きもしっかりしていくんだろうなと思います。にしても、きみは、赤紫蘇がとても似合うね。
橙の時刻

学校主催の基幹講座『色のチカラ探究講座』橙のチカラを先日開催いたしました。
この講座は単発講座で1回1回受けられるのですが、全6色の講座のうち、はじめから受けてくれていた方の6名中5名の方が、継続受講してくださり、現在の5講座目まで受講を共にしてくれています。残り1講座となりました。
感じたことを尊重し合い、胸の奥を照らし合うような時間の中で、さまざまな発見をしてきました。
このように重ねてきたことの中での自分なりの発見が、色彩環全体をつなぐ1つ1つのターミナルになっているように思います。ただ暗記する学びとは違い、自分の中のこととして納得できる学び、また人類のこととして納得できる学び、それを本校は追求して22年間やってきたと思っています。
一つの講座の情報量がなかなか多いので、このシリーズは一度受けた講座を、再受講枠で受講することができるようにしています。またそちらも利用して反復学習してくださればと願っています。
基本的なこと、自然の根源となる要素についてしっかりと学んでいくことで、橙色の現象やイメージから、ものを考えていく幅が広がっていくように思います。わずかなものから多くのものを作り上げる自然があります。たった1つのことに注目してみても、そこに宿る宇宙があることは忘れてはもったいないことだと思っています。多くの部品を手にしてその使い方がわからない近代人ですが、自然は逆をいっていて、まず1つの部分がどのように全体と関わっているかを考えてみる視点が、ひいては自然が進化を続けてきたような、創造やアイデアにつながるのだと思います。
私は科学にできることについてはよくわかりませんが、科学ではない反対側の自然ができることについては、伝えていけたらと思うようになりました。それは色が、自然の語ることばだったからです。



太古からある生命の記憶として、古代人たちが橙を何に見てきたのか、何に感じてきたのか、またそれを受けて何に彩ってきたのか、そのことを私たちが私たちを越えた自分ごととして、存在の深みで感じられることがまた面白いことだと思います。それは自然が、いやアートマンが、はたまた創造主が、いやはや神が、橙色をどのようなものに宿したのか、といったところにまで結ばれてくる話ではないかと思います。
私たちの奥底には、古代人も創造主も、植物も動物も、共にしていることがあるのではないかと思うからです。
そこは科学的なエビデンスや実証といったことなどは畑違いなもので、目の前にいきいきと広がる自然現象こそがエビデンスであり、長らく語り継がれてきた神話や童話などの物語こそが、それを疑いようもなく尊重して生活してきた生命歴史からも、私たちひとりひとりをうなづかせることになるのではないかと思います。そういった分野が、色彩のもっているもう1つの分野、色彩学ではない色彩自然学や色彩心理学の分野ではないかと私は思っています。
今日は時間がきたので、ここで終わります。
また『色のチカラ探究講座』を受講された方の感想レポートなども投稿したいです。
学校の畑は、動画がわんさか溜まっています。編集が大変です。誰か手伝ってくださる方がいたら嬉しいですが。なんらかの形で「自然と共に生きることの大切さ」「自然と共に生活をすることの面白さ」を発信していきたいと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました。