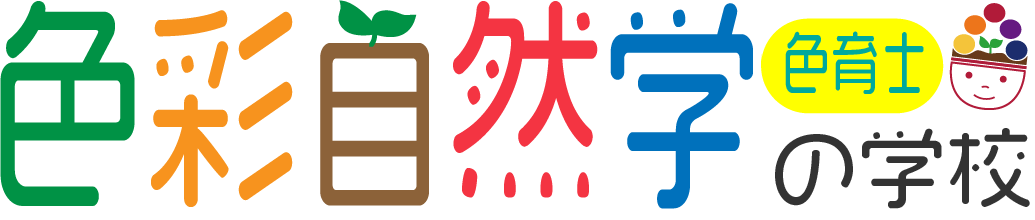野良仕事とは、
”野を良く”し、多様な生物とともに作物がよく育つようにする仕事のことです。

野良仕事3年目。
夏野菜の収穫後の端境期の畑。この夏、日照りが止まず、あまりに草がボーボーと繁っていく畑を前に「途方もないことを初めてしまったんだな」と思うことが正直あった。私の畑はレイズベッド区画で2区画がある。
縦横無尽に生えのびる草たちの勢いと、容赦ない暑さに、心身が負けてしまいそうになる。実際に畑仲間でも長い間休まざるを得ないところがいくつか見られた。
それでも、野良仕事は私の中に根付きはじめていて、やっぱり現場に足を運んで、自然が何をしようとしているのか、見ることだけでもできる限りするようにしていた。
ただ、夏も終わりかけた今日、何かが変わった感じがあった。雲が散り散りにちぎれ始めていることの秋空への変化や風の変化、そういうことだけではなくて、自分自身の内面のことだと思う。
内面に変化がくると、外界がもっと変化していく。
ミントやバジルやら雑草やら、ボーボーに生えている私の畑の隣には、慣行農をしているおじさんの、土がきれいに整備された畑があった。
その私とおじさんの2つの畑の境に立って、ぼんやり眺めていた。
私の畑の方では、クマバチやアゲハやウリハムシや糸とんぼ、バッタ、トカゲまでいて、かさかさと動いているのがわかる。鳥もうちの畑に来ては、何かをつついて飛んでいく。
おじさんの畑の方では、土の茶色がきれいに見えている。整理されていて、1つ1つが輪郭がはっきりわかって、見ていて気持ちがいい。すっきりしている。
私の畑は本当に、ある意味でカオスだった。いろんなものがいろんなものを繋ごうとして動いている。
まだ3年目だからきっとまだまだなんだろうけれど、生態系がすくなくとも豊かに動いていることを実感した。生き物がたくさん動いていて、嬉しかった。
それが、なんとも不器用な生き方をしている自分をも、なんだか許されているような気がして、自分の畑にいられることを嬉しく思った。
これは、自分がやろうとしていることがきっと間違いではないことが、”体でわかった瞬間”だったのかもしれない。ここまでくるにも時間がかかった。まだこれからも時間がかかるだろうと思う。
今はまだ、周りで畑をやる多くの重鎮たちに、土に草が生えていないことが美徳のように語る風習が残っている。「あんたはきれいにしてんなぁ。」とか、「そんなん化成肥料いれときゃええねん」とか。「化成肥料ぱらぱら入れときよ」は、しょっちゅう聞く言葉だ。
私は慣行農を営むことを攻める気はない。農薬や化成肥料を使っている方に、「そういうやり方なんだな」と思うだけで、その人と討論しようとかどうしようとかは思わない。
ただ、私は、誰がどうであれ、土が土らしくいられることを尊重するやり方をとりたい。作物たちも土から尊重してもらいたいだろうと思う。そして、その先に、土がなくなっていく地球、温暖化している地球に、歯止めをかけたいことがある。たとえば死ぬまで1人でこれをやることになるんであっても、知ってしまったらか、やるしかない。この輪が広がるのであれば、それはそれでありがたい。
自然農とは、自然と一緒に歩く農、自然の流れに寄り添う農なわけだ。
野良農とは、”野を良く”し、多様な生物とともに作物がよく育つようにする農なわけだ。
自然に寄り添うというのは、実際に実行してみると、心が寛容にならざるを得ない。生えるものは生やしていこうと思うわけで。それには諦めがいる。自分を振り返って、あの頃の自分にはそういう諦めはひょっとするとできなかったかもなと思う時期がある。諦めた途端に違う世界が開けてくることを、今は知った。諦めた先に道ができる。でもそれは、こだわり抜いたからこそということもあるのではないかと思う。
少しの怪我やハプニングにも、強くなってきたと思う。
草の生える勢いを、自分も体で感じて受け止めることが必要なんだとも、なんとなくわかった。夏はこういうことなんだよ、と。それから、さて、どうする?と自然に尋ねられる。自然と共にいきようとして、求められるのは、やっぱり「対話」なのだと思う。私は”まるまま自然”というわけではないし、自然の流れにのっかることのできる自分を培いながら、自分としてもどうしたいかということをその流れの中で表現する、そんな協奏曲が畑になる。


私はこの夏にできてくれたいろんな作物があって、それはナスやトマトやゴーヤやオクラやピーマンやきゅうりや、書けばきりがないけれど、それらの残渣が土に還ることを思っていた。彼らは土から生まれたのだから、土に還りたいはずだ。残渣を細かく砕いて土が分解しやすい形状にしていく。自然の流れを尊重して、少し人間が手伝うことで、また土が養分を蓄えて、冬の人間の生活へと協力してくれる。
草木や自然がやろうとすることをできる限り聞いて、促す、手伝う。それが里山の役割だったのかもしれないし、野良仕事の中身なのかもしれないと思うようになっている。


先の1つめの写真はトマトの軸で、硬くて粉砕するのも力がいる。そういうのは、きっと土も同じで、分解するのに時間がかかるだろう。それでも、分解するのに時間がかかるだけの養分をこの軸はたっぷり持って枯れていくんだろうと思うから、畑の端っこのほうに積んでおく。じきに乾燥して枯れてきたり、糸状菌のようなものが出てくると、土の中に還しやすくなる。
2つめの写真は、初めて今年栽培したニンジン。初めての栽培は、やっぱりこんなもんだ。間引き方もわからなかったから、株間が狭すぎた。こういう失敗が、体に残る。次にどうしたらニンジンにとっていいのかが行動になってくる。頭でわかるのと、実際に体で知れることは違いが大きい。
もちろんこれもいただきます。心からの「いただきます」が自分の中から声になって出てくることが、心地よい。この人参も、きっと土臭くて美味しいだろうと思う。自分にとっては、ですが。

見た目は全く無秩序で、草がボーボーかのように見える場所だけれど、この場所に、90cm×2mほどの畝が草の下にこしらえてある。あたり一面に生えていた草を、10~15cmほどに裁断して、土の上に敷いた。敷き草が分厚いほど、微生物たちは棲家として喜ぶし、冬の寒さも凌げる。土にとっていい環境づくりにもっと協力したい。まだ夏野菜の残り、オクラが生えている。

今年の夏は、ナスの木ときゅうりがとても元気で、たくさんの実をならしてくれた。私は器用ではないので、「今年はナスときゅうりのことをよく知ろう」と決めていた。一年目と比べてみると、収量が雲泥ほどの違いがでたと思う。でも、ししとうやピーマンのことは正直ほったらかしになってしまって、観察や整枝ができなくて、写真のように実が混みあってしまった。ししとうが思うように大きくなれない状態だ。来年はししとうとピーマンも観察しようと思う。
私がやっている仕事はお金にならないものばかりだけれど、食べるにはあまり困ることがない。なぜなら農を取り入れているから。今は家に追熟中のメロンが数個転がっている。メロンもスイカもイチゴも、今年は収穫できた。きっとこれからもっと土から旬の作物をもらって、体を作ったり維持したりすることになる。きっと健康にも悪くないだろう。
色や自然や農を通して、これからもまだまだいろんなことを学ばせてもらおうと思う。
髙橋水木主催の”巡りのある暮らしのコミュニティー「IRORI」”にご入会を希望される方は、info@colorpsychology.jpまでメールしてください。
・「IRORI」へのご入会は無料、コミュニティールールへの同意が必須条件
・「IRORI」内の講座やイベントの参加には、各講座やイベントで定められた参加料が必要。
〈色彩自然学の学校〉のイベントや体験学習などに一度ご参加いただいている履歴があると、比較的スムーズにご案内できます。