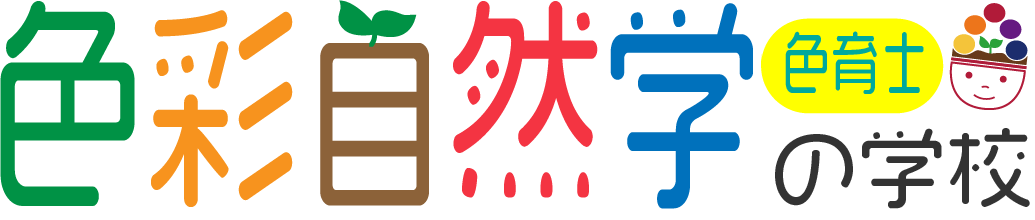《童話づくりとわたしの心理学》講座(全4回+個別面談)が終了しました。

「さて、それはまた次のおはなし…..」
そういう具合に、終わりを迎える童話を、いくつか思い出す。
それを読むたびに思うのは、私たちは現実に戻らなければならないということだった。
こないだ読んだ童話の結末も、さんざん冒険したあげく、気づけばいつものベッドの上で寝ていて、目が覚めた。
童話は本当によくできている。空想や妄想とはわけが違う。
たとえばプロの童話作家は、相当に強い意識の力をもっていると言われている。創造的、かつ無作為に働きかけてくる己の無意識に巻き込まれても、それと対峙しながら、なんとか言葉でとらえて、1つのまとまりとして物を語っていく資質と精神を鍛えている人だと言える。空想と妄想は、そのどちらかがどちらかに負けてしまうことでもあるだろう。
私たちが心の深みで、どのような広がりをもとに生きていて、私を超えたものと繋がっているか、またそれが現実とどのように結びついていくのか、それを冒険させてくれるところが、童話にはある。それは生命として、全体に生かされている証でもある。
昨今、総合医療に光があたってきた。「全体性」という言葉にも光があたり、近代科学を追いかけた時代は、くるところまできたのかもしれないと思わされる。
私たちは、あえて、ゲーテやユングも仲間にいれさせてもらうけれど、この学校に携わる決して多くはない仲間たちも含み、どれだけ長く「全体性」ということに注目し、そこから働きかけ、生きる活動で大切だ、色彩でも大切だと言い続けてきただろう。色はまさしく全体性でこそ息づいて、人のそばにある。
今回、開講できた「童話づくりと心理学」の講座は、彼らに学びの道に入ってもらう中で童話についての認識を広げ、一定のルールをかかげた童話をつくってきてもらうことになっていた。なぜなら、それを自分の心の世界の話として読み解く仕掛けがあるからだ。それにより、「心理学」ということが言える。
自分の童話を、外からやってきた無関係のもの、として扱うわけにもいかず、内界の物語として、たとえ面倒でも1つ1つ声をひろって読んでいく。それができるためには、長らく研究してきた環境づくりと童話への意識の変革と、童話作りのルールが重要な鍵となる。私の提供は、不十分だっただろうと思う。いつもそうだが、完璧にやり遂げられた、とか感じたことがない。
話は戻るが、「当事者」にならずに童話を読めば、「部分」を追いかけることだけに集中してしまい、意味がぶつぎりで満足できないことが起こる。「意味のない童話だ」「つまらない童話を書いてしまった」、と本人が言い切ってしまうことだって起こり得るだろう。
でも、童話の主人公や登場人物になっていくことで、(これを対象的思惟という)「当事者」になれば、結びついて仕方がないものが自ずと結びついて感じられてくる。
こういった「切ってはいけない性質のもの」「切っては死んでしまうもの」が私たちのそばにずっと働いていると私は思うし、意外とこういった性質のものが、生き生きしていなければ、自分という存在があまりにあっさり味気なく感じてしまうことが起こると思っている。無味乾燥という言葉もあるけれど、生命にはたらく全体性には、きっともう片方の、地下室にある環境のような、湿気や暗がり、まとわりついてくるようなものが、ついてまわるのではないかと思う。
長くなってしまったが、今回、彼らの童話を5人分5作を、期間中読み続けた。私は半端なく繰り返し読むほうなのだが、童話ごとに、主人公と私の境界がなくなるくらいになることもあって。自分の感情なのか登場人物の感情なのかわからないものが押し流れてくることもあった。そこまですることはよくないと感じる自分もやっぱりいるし、でも、そこまでしなければこの童話の世界に生じる本当の課題や喜び、そしてこの王国がどのような運びになっていこうとしているのかなど、感じられるはずもないと思う自分もあった。
講座内でまず、自分の童話を自分で読み解いていく時間がある。その時間に、彼らはいろんなことを見つめながら、自分で見つけていくものを拾い上げていく。その時間は、自分の足で歩き、自分の心をつかう時間で、私の講座ではかなりの時間をそれに費やすようにしている。そして、最後に私と個別分析の面談に、希望者のみ入るようにして、童話を”たましいの現れ”として受け取ることに接近していく。
描いた絵を眺めながら、言葉で書かれたものと、そこにあらわれてはいないけれどあるはずのもの、その丸ごとを味わい尽くしたいと願う想いが高まっていく。それができたとは言えない、できなかった。でも、私でできる今のベストは尽くしたと思います。
みなさんの感想文もいただけると思うので、また別の形で報告しようと思う。
受けてくれたみなさんが、自分でつくった童話をいつかは愛おしく思えることを願いながら、いつかふと思いだすことがあったら、それがまた続いている物語ということの証になることと思います。
現実に戻るとそこは生活ですが、私たちは現実ではないところでも生きていて、その総合が「私」という存在になるということではないかと思います。
現実をめいいっぱい自分らしく生きるためには、現実ではないところの息遣いも感じていてください。
これにて終了です、ありがとうございました。