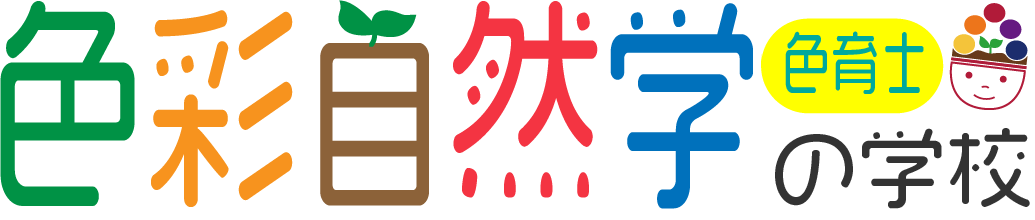先日、全5回中、2回目の「童話と心理学の講座」がありました。
今回講座でとりあげたのは、グリム童話の「カエルの王さま(鉄のハインリヒ)」でした。
グリム兄弟が、初版から決定版まで、この物語を童話集の1作目に持ってきたという、おそらくは相当な思い入れのあった作品だったのではないかと想像します。
この物語がなん度もなん度も人々の心を通ってきた中で一体どんなことを人々にもたらしてきたのか。
我々においても、一体この物語のどんな部分にどんなこころがくすぐられるのか、ざわざわするものなのか、そこを追いかけていくことが面白い時間だったのではないかと思います。
受講生それぞれに、読み方や心の動き方がありました。それが、今人生のどんな時かということを照らしだしてくれるものでもありましたから、ひとりひとりの読み方や感じ方こそ、尊重されるべきものだと思います。私たちには、抵抗したりコントロールしたりすることのかなわない、本能に近いなにかがあって、ある意味で、肩の力をぬいて、その自然道のようなものを歩いていかねばならない時がそれぞれにあるのだと思います。
色彩自然学には、”心の自然”ということを研究したユング博士の無意識のもつ元型という概念が、色の普遍的イメージを追いかける際にやはり息づいていると感じます。そういったことが童話に働いているし、いかに童話が人のこころの深みの動きをとらえ、それを素朴に、そして露骨に、見せてくれているかを感じます。
カエルの立場で読むのか、お姫さまの立場で読むか、はたまた、ハインリッヒの立場で読むのかで、違った景色が見え始める物語でした。そんな童話のもつ広い野に放たれたようで、わたしたちは一体どんな童話を作るのだろう、どんな物語が動き出し、溢れ出すのだろう。どれだけのことを、我々はぼろぼろとこぼれ落としながら、生きてきたのだろう。どれだけのものを取り戻したいと、たましいはねがっているのだろう。
すこし怖くてもあり、楽しみでもありますが、なんとも言えない童話制作の期間を、私たちは次の講座まで過ごすことになります。
読んでくれた方、ありがとうございました。