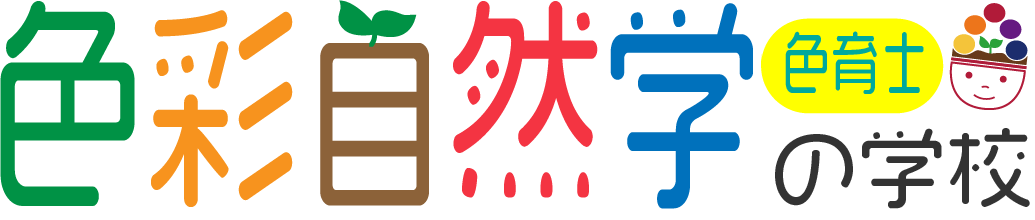暦は立秋を迎え、秋が立っているというのに、
こんなにもあたりは旱、水が恋しい。
北海道までもが40度を超え、地球温暖化が深刻に進んでいる。
「私ごときに何ができるか」という、その捻くれた根性を、断ち切るべきだと思った。
地球温暖化に加わってきた当事者であったことに、まず気づくこと。
そして、無理なくできることを、続けて還していくこと。
私は、40歳になって、土の回復を手伝いたいと、畑を選んだ。
自然菜園に取り組んで、化成肥料を使わず、野菜残渣などの有機物を堆肥として循環させていく。
これにより”腐植”が増え、土が増える。少なくとも、土が土本来の力を保った状態でいられる。
土は二酸化炭素を地中に貯蔵してくれる。温暖化と密接につながっていて、そもそも、温暖化が進んでいるのは、土が損なわれているからだと知った。
昨今すごい勢いで、世界の土が減っているという。
「私たちは、土を消耗する形で繁栄してきた」と福島国際研究教育機構ユニットリーダーの藤井 一至さん。北米のチェルノーゼム地帯では、過去100年で黒い土の厚さが半減してしまったことを伝えている。
私たちは土の力を尊重する精神をどこで見失ってしまったんだろう。
見栄えの良い野菜を追求し、甘く美味しい果物も追求し、一面に咲く観賞用の花を追求し。
その背景で、化成肥料などで酷使され、ごみとして燃やされ、使い捨てのようにされるその土の気持ちは、いかばかりだろう。
地球だけが作ることのできる土には、そのスプーン1杯に、100億個、1万種類を超える細菌がすんでいるという。その土から、ほとんどの食べ物をいただいている私たちがいる。
畑をやって3年目。やってみるとこれは「労働」でもある。相当なエネルギーも使う。この猛暑では、人間も作物もかなりの影響を受ける。生きるための活動、と書いて、生活なのだけれど、生活のなかに畑を取り入れていくその大変さは、やってみなければわからない。それでも、今まで感じたことのない自然や人への感謝の気持ちや、足るを知る精神が、私の中に取り戻されていったように思う。
次の写真は、腐植を増やす様子で、畝や道の端に無尽蔵に生えゆく雑草たちや、収穫後の野菜残渣を材料として、「草マルチ」という方法で実践している。

枯草や雑草をたばね、短めに裁断後、畝に厚さ3cmくらいになるように戻し敷く(左側のナス苗の下は、草マルチを敷いたあと|右側のナス苗は、草マルチを敷く前)。草マルチがあることで、微生物たちのすみやすい環境を保つ方法で、雑草が次第に時間をかけて腐植となり土の一部にかえっていく。土は、腐植によって増え、新しい野菜を育てる元気を回復する。慣行農業では、ここに化成肥料や有機堆肥を施して、土からみれば外からその力を押し付けて、酷使する形になる。
次の写真は、いちごを育てていたあとの畝に、草マルチをしたあと、米糠をかけて腐植化を促進している。四季なりいちごの苗が、まだ元気だったので1つ残して草マルチをおこなった。

右左に見える雑草たちも、じきに刈りとって適当な長さに裁断し、草マルチの資材として使っていく。畑にいらないものはなに1つない。この畑から生まれるものはすべて、この畑に還っていく。その考え方が、私は好きなのだと思う。
生活の中に、コンポストを取り入れていく。それもいい。巡っていくことを考えて生活をする。
生活の中に、自分たちらしく、少しでも。