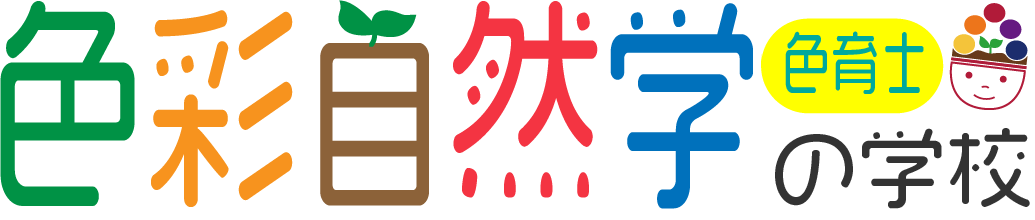川の近くに引越ししてきてから、よくトカゲを見る機会が多くなった。
今、畑も端境期で作物が少なくなり、土づくりをしていたところ、足場の下に、どうやらニホントカゲが巣を作っていたようで、顔を見せてくれたところを撮影した。そこからはもう土づくりそっちのけで、彼が出てくるのを待っては撮影して、を繰り返してしまった。
まず、驚いたことがあって、体の色の「赤さ」に驚いた。
あと、ニホントカゲなのに、あの青光りしていた尾っぽや虹色ののような背色が見当たらなかったことにも驚いた。いつも見るニジイロトカゲよりもずっと大きい個体に感じた。
ニホントカゲは、どうやら幼体と成体とで色が変わるらしい。私が出会ったこのトカゲはどうしてこんなに赤い色をしていたのか、それを追いかけてみた。
幼体と成体で色が変わる生き物
ニホントカゲは、
幼体、つまり私たちでいうところの生まれてから成人になるまでと、
成体、つまり大人になった頃、では、色が変わるという。
そういう生き物はこのニホントカゲだけではなくて、たくさんある。むしろそれが生き物として自然な、成熟の表し方なのだろうと思う。
たとえば、青虫も、幼体だけでも体の色がかなり変わっていく。最初は黒褐色の点のようで、次に鳥の糞に擬態したような白黒のような色彩になる、その後に葉っぱに紛れられる緑色になり、成体になる前には蛹化し、茶褐色の蛹になる。最後には鮮やかな羽色を持つようになっていく。その体色が変わるごとに、脱皮していく。


私の大好きな鳥たちも、幼体と成体では色が変わってくるものがある。たいてい、成体になることで色がくっきり鮮やかになったり際立ったりすることのほうが多いのではないか、と感じている。特に交尾期に入ると、オスは鮮やかな羽色や姿形で、メスの気をひこうとすることがある。
話は戻るが、今回見つけたニホントカゲ、幼体はニジイロトカゲと呼ばれているそれである。

あおい尻尾にどうしても目が惹きつけられる。どうしてこんなに青いのだろう。
なぜ、ニホントカゲの幼体の尻尾は青いの?
一説によると、尻尾に捕食者の注意を向けることで生き延びるためだ、という。
確かに、草むらや大地の近くにいるとこの青が光っているのが目立つ。捕食者に襲われたとき、彼らは尻尾を切って(自切)生き延びる技をもっている。特に幼体のころは、体が小さく力も弱いため、この自切によって、自分を守ることが重要なのだろう。
捕食者の注意を尻尾に向けることで、いざとなったときに自切して、生き延びるため
こういうことを知ると、”自然”は、そのものがそのものとして生き延びるために必要なものを、ちゃんと醸造できるように、すでに与えているんだなぁと、その懐のようなものに感服する。
成体になると、尻尾の青はくすんでいき、全体が褐色になり、周りの風景と溶け込むようになっている。私が見つけたニホントカゲも、このように褐色づいた成体であることがわかった。

どうして赤いニホントカゲがいるのか?
さて、やっと本題になるが、今回出会ったニホントカゲに赤みを感じるのは、どうしてだろうか?
どうやらこれは「婚姻色」ということと関係があるようだ。
婚姻色って何?
婚姻色とは、一般的には、動物の繁殖期にだけ現れる体の色のことを言うそうだ。
魚、両生類、虫類などの原初に近い動物で、雄に見られることが多い。
動物だけでなく、植物も果実を実らせたり、いわゆる生長して成熟し雄蕊と雌蕊が交わって結実することに向かう時、赤みを帯びていく。
色彩自然学でも学ぶことだけれど、自然というのは、秋に向かって絶頂になって、冬には死と再生の冬籠の儀式が行われているように、赤みを帯びていくことで次なる生命のバトンをわたしていくことが、本質的に見られる。
今回出会ったニホントカゲも喉のあたりが赤い。出会った私の体感では、全身があからんで見えるほどだったから驚いていた。

ちょうど、繁殖期にあたっている可能性が高いことがわかった。
余談になるが、私の好きなカワウは、繁殖期になった合図として、頭部に白い羽が目立つようになるらしい。その頃の写真が見つかったので一緒に掲載しておきたい。

まとめ
自然に生かされながら、その生命を全うしていく中で、さてバトンを渡そう、という時に、その準備としても質的な充足のようなことが起こるのだろうけれど、それが色に表れて、体色に溢れ出ていく。
ニホントカゲのように、赤い色が体に満ちていく感じを自分自身に想像したとき、やっぱりなにかを残していこうと、情熱的な行動をとる自分がいる気がした。
自然も、色もほんとうに面白いし、すごいなと思う。
読んでくださったありがとうございました。