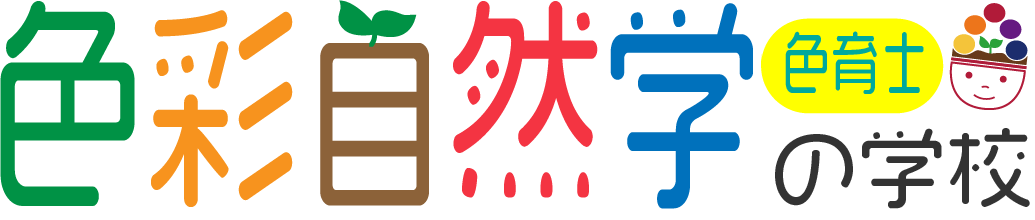「私なんて、存在していいのだろうか。」
という避けられない絶望の淵に、立たされることがある。
もうこれ以上、一寸の希望ももつことができない絶望や虚しさに、胸を詰まらせ、血の気もひいたような日々が何度かある。
悲劇的だとか周りにどう言われようが、そう自分が思うことが、どれだけきらきら見える人生を歩んでいる人にも、それぞれに実はあるのではないかと私は思う。
生きることは、綺麗事ではいかない。
めめしく、よわく、ずるく、何かのいのちの上に立っての今がある。
でも、そうやって存在の怯えの淵のようなところに立ってはじめて、見えてくることもある。
弱いもの、怪しいもの、小さなもの、脆いものが、私の中を蠢いていることを、生き生きと感じる。役に立たない、強くあれ、と捨て置いて無視してきたいろんな自分自身を、改めて拾い上げ、掬い上げ、抱きしめられるようになると、うっすら違う視界がひらけてくることがあるのではなかったか。
色は、光と闇のあいだに広がる。
光が闇を、闇が光を、ありえないほどの乖離した二つの隔たりを、受け入れ合う道のなかに色彩は広がっている。そのグラデーションに、心を揺らさないはずはない私たちは、時折夕日に祈りをささげている。
私たちは誰一人もれず、この光と闇のあわいを流れるような深い深い河をもっている。
二つの岸を断絶する坩堝のような深い河から、それをつなぎとめようとする1つ1つの何かが、象徴となって色を帯びていく。
自然の言葉として、色を受け止めていきたいとすることは、魂の声をきくことでもある。
魂ということにおいては、万物が溶け合って共にしているものがあるのだろう。
私たちはきっと、もっと声が聞きたいのではないか。
自然の声、魂の声を、もっと聞いて、全身全霊で生きたいのではないか。